こんにちは、介護事業部の大村です。
5月25日より募集をしてまいりました、初任者研修講座ですが、
おかげ様で定員数20名に達しましたので、本日を持ちまして募集を締め切らせていただきます。
次回の募集は10月頃を予定しております。
よろしくお願いいたします。

こんにちは、介護事業部の大村です。
5月25日より募集をしてまいりました、初任者研修講座ですが、
おかげ様で定員数20名に達しましたので、本日を持ちまして募集を締め切らせていただきます。
次回の募集は10月頃を予定しております。
よろしくお願いいたします。
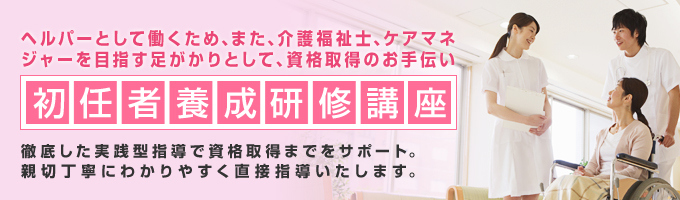
平成25年度上半期の初任者研修養成講座(ヘルパー2級相当)の募集を5/25より開始いたしました。
4月よりホームヘルパー2級養成講座が、介護職員初任者養成研修に移行となり、より良いサービスが提供されるよう、段階的に知識や技術を習得できるようになりました。
研修終了後、初任者研修課程修了者(旧ホームヘルパー2級と同じ)として愛知県に登録され公式認定されます。
介護施設や訪問介護で働くこともでき、3年間の実務経験と、実務者研修を修了に介護福祉士の受験資格が得られ、介護福祉士取得後には介護支援専門員(ケアマネジャー)への道が開けます。
定員は20名です。
定員になり次第、締め切らせていただきますので、参加ご希望の方はお早めにどうぞ。
4/6(土)の講座では、演習終了後にiPad体験会を開催し、受講生の皆さんにiPadの便利さと楽しさ、介護業界においての必要性を知っていただきました。
発売から爆発的な人気を誇るiPad。ネットや写真・動画鑑賞、電子書籍など、魅力的な機能が満載で その実力はスゴイと定評があります。
受講生の皆さんが晴れてヘルパーとして仕事に従事した際、記録書書きやケアプランばかりに留まらず、iPadを使ってお年寄りとのコミニュケーションを取ってもらうことができます。また利用者の遠く離れたご家族との連絡手段として、今や介護業界においてiPadは無くてはならないものとなって来つつあります。
 初めてiPadを手になさった方のために、まずは簡単なボタン操作や文字入力の仕方をご紹介からスタートしました。
初めてiPadを手になさった方のために、まずは簡単なボタン操作や文字入力の仕方をご紹介からスタートしました。
そのディスプレイの美しさは見てびっくり!! そして、指先ひとつで、簡単に操作ができてしまう手軽さがイイんですよね。
スマートフォンを持っていらっしゃる方は尚のこと、初めての方もほんの数分で、カメラ機能を使いこなしてしまわれました。
「え~っ。恥ずかしいわ。」と皆さん照れていたものの、その写真を加工して作品にしてみよう…と、その楽しさにすっかり夢中に♪
その写真合成に便利なのがフォトファニア(Photofunia)というアプリ。
気に入った写真を選んでクリックしたら、合成したいベース写真が出て、その人物のところが、自分の選んだ写真と置き換わり合成されます。
その出来栄えに大満足で、メールで送ってもらって保存したいわ~と喜んで下さった方もおみえでした。
今回は初めての体験会で、約40分という短い時間ではありましたが、受講生の皆さんに和気あいあいと体験して頂けて、当社スタッフもとても良い時間を共有させていただけました。
ご協力くださった平尾先生、受講生の皆さん、ありがとうございました。
当社では、喫茶ベストワンで定期的にこのようなiPad体験会を開催しております。興味・ご関心のある方はホームページにてご検索下さい!!
3月16日に行われました養成講座の様子をご紹介いたします。
今回の大きなテーマは、「食事介助」です。
人間に とって食事は生命を維持する上で欠かせないもので、味覚・視覚・嗅覚・触覚・聴覚の五感で味わってもらう大切な行為です。
とって食事は生命を維持する上で欠かせないもので、味覚・視覚・嗅覚・触覚・聴覚の五感で味わってもらう大切な行為です。
その上、病床から離れて食事をすることは、利用者の気分転換や生活リズムを整えることにもつながります。
しかし高齢者の場合、諸機能の低下から誤飲や窒息などの事故も発生する危険性があるので、細心の注意が必要になります。
1枚目の写真のとおり、受講生は実際に交代で利用者役となり、介助を受けてみました。
「口をあけたままではお茶を飲みこめない。上を向いていては飲み込めないとは、体験してみないとわからなかった。」という意見が出ていました。
 2枚目の写真では、利用者役がアイマスクを着用し、目が不自由な方の食事介助を演習しています。
2枚目の写真では、利用者役がアイマスクを着用し、目が不自由な方の食事介助を演習しています。
食事をする前には水分を取ってもらう、あくまでも介護者の都合で次々と物を運ぶのではなく、利用者の顔色を確認しながら介助していくことが大切です。
パジャマや寝巻きの着脱は、半身麻痺の利用者でも工夫すればご自分でできる動作も多くあるもので、介護員はご自分でできない部分を介助するという姿勢が必要だと学びました。
演習第二日目の3月3日に行われましたヘルパー養成講座の演習の様子をご紹介いたします。
主に、入浴介助の必要性を学び、その手順 技術を得ることを目的としていました。
 体を清潔にし血行をよくするとともに、利用者の身体状態を観察する、気分転換をしていただくためにも、入浴は大変重要な意味を持っています。
体を清潔にし血行をよくするとともに、利用者の身体状態を観察する、気分転換をしていただくためにも、入浴は大変重要な意味を持っています。
入浴介助における観察では、バイタルチェックで顔色、体温、脈拍、呼吸、血圧、ご本人の訴え、異常がある時にはすぐに報告、相談をする。
実習生のみなさん、真剣な面持ちで利用者役に足浴を行っていました。
ヘルパーとしての知識、技術も勿論のことながら、人と人とのふれあいを大切とする仕事ですから、利用者のプライバシーを配慮した上で介助し、急な温度変化等で負担をかけないないように…と細心の注意をはらって演習していました。
演習はあと三日間。
第三日目は食事介助の演習、第四日目はおむつ交換、最終日は肢体不自由者等の歩行介助です。高齢者疑似体験セットでの体験も予定しております。